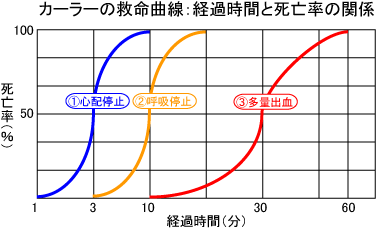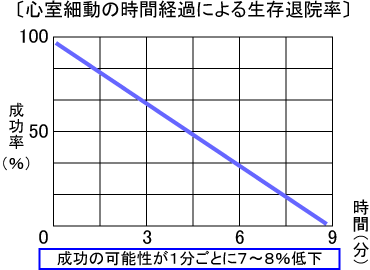|
|
|
 |
|
|
|
|
|
「カラーの曲線」 |
|
| この図は、心臓停止、呼吸停止、出血などの緊急事態における経過時間と死亡率の関係を示したものです。例えば、心臓停止では3分間放置されると死亡率が約50%に、呼吸停止では10分間放置されると死亡率が約50%になります。このことは、緊急事態が重大であるほど早く適切な処置をしなければ、死亡者が増加することを意味しています。 ※放置時間が長かった場合には、手当の意味がなくなるというわけではありません。 早い時間に手当が開始されれば、それだけ救命率が高くなることは当然ですが、放置時間が長かったとしても、少しでも蘇生の可能性があれば、その可能性に賭けた積極的な手当が望まれます。 |
|
|
緊急ケアが必要な場合およそ4分で人間の脳への悪影響が出ると言われております。起こってはならない事ですがもし万が一あなたが緊急ケアを行わなければならない事態になった場合にEFRで身に付けた技術を迅速かつ適切なケアを患者に行えるはずです。
1998年の調査によると、国内の救急隊が通報を受けてから現場の到着までに、平均約6分かかります。交通事情が悪い地域、救急隊の出動が頻繁な地域は、8分以上みなければならない場合もあります。世界的に見ると、この到着するまでの数値は大変優秀でありますが、仮死状態からの救命率は、わずか3%しかありません。それでも数年前日本にも救急救命士が登場、救命率が1%から3%に上がりました。それに比べアメリカでは現場到着までの平均時間はかなり遅いのですが、仮死状態からの蘇生率は、なんと20%〜30%もあります。アメリカでは一般市民にCPRが普及しており、7,000万人の市民が米国心臓病学会の主催する初期救命処置の講習を受けていると言われています。一般市民による迅速な初期救命処置が、高い救命率になっているのです。先に述べたように、心臓や脳の病気で死亡する人が多く、続いて不慮の事故の死亡が続いています。これらの原因で死亡する患者の大半は、救急蘇生法(ファーストエイド)でケアされるべき対象者です。なぜ日本の救急隊が、到着までに平均6分で来るほど優秀にもかかわらず、救命率(蘇生率)が上がらないのか?それは、人体が呼吸や心臓停止になってから1分後に人工呼吸ができた場合では約97%の人が蘇生しますが、3分後では75%、4分後では50%、5分後ではわずか20%、8分後ではほとんど助かりません。どんなに優秀な救急救命士がいても、5分30秒後では15%しか蘇生しないのです。ですから、救急隊員に引き継ぐまでの時間は大変重要なのです。そのためにも、アメリカのようにたくさんの人が救急蘇生法(ファーストエイド)を覚えて実践できれば、患者の近くにいる人が一刻も早く手当てをすることにより、救命率が高まるのです。 |
|
|
『AHA心肺蘇生と救急血管治療のための国際ガイドライン2000参照』
|
|
| この図は、心室細動になってから除細動を行うまでの時間経過と生存退院率の関係を表しています。除細動をするのが1分遅れると、生存退院率が7〜10%の割合で下がってしまいます。現場に居合わせた人が、その場で早期に除細動を行うことが重要となります。大切な事は、AEDがその場にあるかないかに関わらず、救急車が到着するまで心肺蘇生法を続け、救命の鎖を継続することです。 | |
| 心室細動って何? 心筋梗塞など心臓に疾患を持つ人が突然倒れた場合、心臓の筋肉がブルブルと小刻みに震えている場合があります。この状態を心室細動とよんでいますが、このまま放置すれば、心臓はポンプの役割を果たせないため、短時間に意識を失い、その後、死に至る可能性が高くなります。 AED(Automated External Defibrillator)って何? AEDとは、英語の頭文字の略語で、自動体外式除細動器のことです。 Automated 自動 External 体外式 Defibrillator 除細動器 AEDは、高性能の心電図自動解析装置を内蔵した医療機器で、心電図を解析し除細動(電気ショック)が必要な不整脈を判断します。AEDは、小型軽量で携帯にも支障がなく、操作は非常に簡単で、電源ボタンを押すと(又はふたを開けると)、機器が音声メッセージにより、救助者に使用方法を指示してくれます。また、除細動が必要ない場合にはボタンを押しても通電されないなど、安全に使用できるように設計されています。 除細動って何? 「突然の心停止」の原因となる重症不整脈に対し、心臓に電気ショックを与え、心臓が本来持っているリズムに回復させるために行うものです。 |
|
|
『救命の連鎖』
|
|
| 「突然の心停止」を起こした傷病者では、「救命の連鎖」が迅速かつ連続的に行われることが重要です。日本における従来の「救命の連鎖」では、一般市民の行う救命手当ては、早い119番通報と心肺蘇生法に限られていましたが、早期除細動の重要性の観点から、平成16年より、医療資格を持たない一般の人でもAEDという機器を用いて除細動を行うことが認められました。一般市民にAEDの使用が認められたことに伴い「救命の連鎖」の3つ目の輪が一般市民の救命手当てに含まれました。一般市民の行う3つの輪が、傷病者の救命率の向上に大きく関わってくることが期待されます。 | |
|
AED使用にあたり厚生労働省からの4つの条件 1. 医師を探す努力をしても見つからない等、医師等による速やかな対応を得ることが困難であること。 2. 使用者が、対象者の意識、呼吸がないことを確認していること。 3. 使用者が、AEDの使用に必要な講習を受けていること。 4. 使用されるAEDが、医療器具として薬事法上の承認を受けていること。 |
|
|
|
|
|